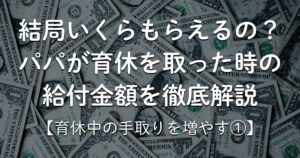「男性が育休を取る」と言うと、近年では徐々に一般的な話題になりつつある一方で、実際にどのくらいの長さを取れるのか、どのようなステップを踏めばよいのかといった“具体的なところ”がわからず、尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか。
特に、周囲の男性社員にまだ育休取得の前例がない場合や、社内であまり事例が共有されていないケースでは、なおさら行動を起こしづらいものです。
私は、男性としてはまだ珍しい、1年間の育休を取得しました。
その経験をもとに、タイムラインや根回しのコツをお伝えできればと思います。
正直、男性育休を取ると決めるまでには多くの疑問や葛藤がありました。「取りたいけれども、周りは取っていないので目が気になる」「実際に取り始めたら業務はどうなるのだろう」「そもそも育児休業を取ると会社に迷惑がかかるのでは?」といった不安を抱えた時期もあったのです。
ですが、やはりどうしても1年間の育休が取りたいと覚悟を決めて行動した過程を振り返ると、そのプロセスで社内のサポートや応援をたくさん受け、同時に家族や自身のライフスタイルにも大きくプラスに働いたと感じています。
本記事では、私が「男性の長期育休」をどのように具体的な行動に移していったか、そのタイムラインを軸に詳しく解説していきます。育休を取得するために上司や人事への相談をどのタイミングですればよいのか、どのように周りに話を進めればスムーズにいくのか――そういった疑問や不安に対する一つのモデルケースとして、ぜひご覧いただければと思います。
なぜ長期の男性育休が必要なのか
まずその前に、長期にわたる男性育休の必要性を改めて考えてみましょう。
育児は夫婦二人三脚で
育児休業の本来の目的は「子どもが生まれた後、一定期間、子どもに集中して関われる環境を整える」というものです。
パートナーが出産後、心身の負担を抱えながら赤ちゃんのケアをするなかで、男性も同じように育児・家事に参加することは、夫婦間の負担を大幅に軽減し、子どもの成長過程を最初から共同でサポートしていく上でとても重要です。とりわけ、生まれてからしばらくの間は赤ちゃんも不安定なことが多く、夜泣きや頻回授乳などが続き、心身ともに疲労が蓄積しやすい時期です。
男性がここでしっかりとコミットできるかどうかで、夫婦間の協力体制や家族の絆にも大きく差が出ることを痛感しました。
職場風土・社会の変化に寄与する
日本では、まだまだ男性が長期の育休を取ることに対して「珍しい」「大丈夫なの?」という反応もありますが、少子高齢化が進む社会においては、男性が積極的に育児休業を活用することが企業の持続的な成長や社会基盤の維持にもつながると考えられています。
最近では育児・介護休業法の改正や企業の取り組みの推進などで、男性育休に対する制度面のサポートが充実しつつあります。こうした流れの中で、自分自身が率先して長期の育休を取得し、その経験を社内外にシェアすることは、新しい価値観や職場の風土づくりにも良い影響を与えるでしょう。
自分のキャリアにとってのプラス
「長期の休暇を取るとキャリアに影響があるのでは?」と心配する方もいるかもしれません。しかし、実際に長期の育休を経験してみると、得られるものはとても多いです。
短期休業ではカバーしきれない赤ちゃんとの密度の高い時間を過ごし、パートナーや家族といった“これから先の人生で最も大切となる存在”と向き合う機会は、キャリアにとっても非常に大きな学びになります。
子育てでしか得られない経験や視点は確実に存在します。
新たな視点や仕事以外で身につけられるスキル(時間管理力やコミュニケーション力など)は、復職後にも活きてくるでしょう。
育休を取るまでのタイムライン
では、ここからは本題である「私が育休を取得するまでの具体的なタイムライン」を示します。実際に私が踏んだステップを振り返りつつ、どういった点に注意したか、どんなことを考えたかを補足していきます。
育休取得の7ヶ月前:最も重要なキーパーソンに報告
- 主なアクション
- 最も近しい上司や人事に妊娠を報告する
- 「まだ公にはしていない」と伝えつつ、相談モードで話をする
一般的には安定期に入った頃(一般的には妊娠5カ月目頃)を目安に、上司や人事へ打ち明ける方が多いと思います。
もちろんそのタイミングの方が伝えやすいという方も多いと思いますが、個人的には比較的早めの段階から、自分が育休を取るにあたっての最重要人物1人か2人には頭出しをしておくことで非常にその後のプロセスがスムーズに進んだと実感しています。
ここで重要なのは、「まだ限られた人にしか伝えていないのですが…」と前置きしながら打ち明けることで、相手に“特別にシェアしてもらっている”という印象を与えられ、相談しやすい空気をつくることです。
男性の場合、妊娠が自分の体ではないため、実感がまだ薄い時期かもしれません。しかし、こうした早めの段階で「育休を視野に入れている」というニュアンスを上司や人事に軽く伝えておくと、後々の育休取得に向けた社内調整の土台ができます。上司にとっても、「うちの部署の誰々が、半年後には育休取るかもしれない」と意識してもらえる分、業務や人員計画の組み直しを検討しやすくなるのです。
育休取得の4〜5ヶ月前:人事への詳細相談と育休情報の下調べ
- 主なアクション
- 人事など育休を管轄している部署に「育休を取ろうと考えている」旨を正式に伝える
- おおまかな期間の目安を共有し、社内制度の詳細を調べる
妊娠安定期に入り、出産時期が具体的に定まってきたタイミング(出産予定の4〜5ヶ月前)では、人事とより踏み込んだ話し合いをする段階に入ります。ここでのポイントは「いつからいつまでの期間を考えているか」をざっくりでも伝えておくことです。
「男性育休を取りたい」と言っただけでは、人事担当者や上司は具体的にどの期間なのかイメージが湧かない場合があります。特に男性の場合、育休の前例が少なかったり、過去の実績が“1〜2週間”程度であるケースもあるため、「同じく1〜2週間で考えているのかな?」と勝手に推測される可能性もあります。実は自分は半年や1年といった長期を希望しているのに、この認識ギャップを埋めないまま話を進めると、後々「それは想定外だ」と反発を受けるリスクが高まるのです。
逆に、最初は少し長めに伝えておくくらいの方が良い、というのが私自身の経験上の実感です。長期育休を想定していて、いざ正式に申請するときに期間が多少伸びたり縮んだりしても、事前に大枠のイメージを共有しておけば柔軟に対応してもらいやすくなります。私も最初に9ヶ月程度と伝えておきながら、最終的には1年まるまる取らせてもらうことになりました。結果的に1年間という長期を取得することになったのですが、「ちょっと長期化します」という後出しであっても、周りの理解はそこまで悪くありませんでした。早めに伝えておくメリットをぜひ活かしてみてください。
育休取得の3ヶ月前:関係者への周知
- 主なアクション
- 上司や社内メンター、同じ部署のメンバーなどに改めて育休取得を周知
- 具体的な引き継ぎ計画の大枠を説明
出産の3ヶ月前となると、いよいよ具体的な育休スケジュールが現実味を帯びてきます。ここでは上司やチームメンバーに「いつ頃からどのくらいの期間、育休に入る予定か」を再度共有し、業務の引き継ぎ準備を始めるタイミングです。
この時期に大事なのは、「周囲に話をする順番」と「引き継ぎの段取り」です。上司の理解を得たうえで、チームメンバーに対してどのように周知するか。その際、自分が担当しているプロジェクトやルーティン業務をどのように振り分けるかをあらかじめ考えておき、具体的なシミュレーションをできる範囲で見せると安心感を与えます。たとえば、プロジェクトXはAさんに、定例レポートはBさんに引き継ぐ予定など、具体例を挙げながら話すと「自分が休んでしまったらチームが回らないんじゃないか」という周囲の不安を払拭しやすくなります。
私の場合は、直属の上司・メンターとの面談で「これとこれは引き継ぎ先を明確に決めたい」「時期的にプロジェクトの山場がここにあるので、その前に最終調整を終わらせたい」といった要望をまとめ、それをチームに展開してもらいました。自分の言葉だけでは言いづらいことを上司がフォローしてくれたことで、とてもスムーズにいきました。
育休取得の1ヶ月半前:全社や部門への周知(必要に応じて)
- 主なアクション
- 部署外のプロジェクト関係者や取引先(必要に応じて)などに「何月何日から育休に入る」という情報を伝える
- 連絡窓口や引き継ぎ先をしっかり案内
出産予定日まで1ヶ月半程度になると、正直、いつ生まれてもおかしくない状況になります。早産など予測不能な事態もあり得ますし、パートナーの体調が急激に変化して入院することも。そうしたリスクを考慮すると、「もうそろそろ休みに入るかもしれない」くらいの感覚で社内外に周知をしておくことが望ましいです。
全社レベルでのアナウンスが必要かどうかは、会社の規模や業務内容によるでしょう。部門間やプロジェクトごとの連携が多い職場であれば、ある程度大きな範囲で「〇月〇日から育休に入る予定です。その間の対応は××さんが行います」という告知をしておくことで、相手側もスケジュールを調整しやすくなります。特に取引先がいる場合には、担当が変わることで混乱が生じないよう連絡を徹底しましょう。
タイムラインをスケジュールに当てはめる際のポイント
ここまでご紹介したタイムラインは、あくまでも私が実際に経験した一例です。会社の規模や職種、あるいは妊娠・出産のスケジュールによっても変わってきますので、必ずしもこの通りに進めなければいけないわけではありません。ただし、以下のポイントは多くの方に共通するのではないかと思います。
- 早めの相談がカギ
一番大切なのは「早めの段階で近しい上司や人事に相談する」ことです。男性育休という“前例が少ないケース”を乗り越えるには、時間をかけた根回しと周知が欠かせません。とくに上司・人事への相談はできる限り妊娠安定期に入ったあたりですることを強くおすすめします。 - 「まだ内々ですが…」とお願いする
上司や人事に話す際、「実はまだ公にはしていないのですが…」と一言添えることで、相手に「重要な情報を早めにシェアしてもらった」という気持ちを持ってもらいやすくなります。誰でも“特別扱い”されると悪い気はしないものです。「自分に早く相談してくれたのは、自分を信用してくれているからだ」と受け取ってもらえれば、協力体制の構築がスムーズになるでしょう。 - 期間のイメージ共有は長めに設定しておく
育休取得期間を曖昧にしていると、周囲は従来の慣習や他の事例から短い期間を想定しがちです。最初から希望する最長期間を提示しておいた方が、後々「実はもう少し伸ばしたくて…」と切り出すよりもスムーズに理解を得られやすいです。後で短くすることは比較的ラクですし、トラブルも少ないはずです。 - 引き継ぎ計画を具体的に示す
長期育休を取ると業務が長期間空いてしまうため、周囲がもっとも気にするのは「自分がいない間の業務がどうなるのか」という点です。ここをしっかりと示すことで、「それなら大丈夫そうだ」「ちゃんと考えているんだな」と理解と安心を得られます。 - 柔軟な対応を忘れずに
妊娠・出産はどうしてもイレギュラーがつきもので、予定日より早く生まれることやトラブルで急に入院が必要になるケースもあります。会社側もある程度柔軟に対応できるように調整しておくことが理想ですが、こちらからも「予定より早まる可能性があるかもしれません」と伝えておくと、さらに良いです。
長期育休を取ってみた感想とメリット
この点に関しては別途記事があるので詳細はそちらをご覧いただきたいのですが、
とても簡単に、おもにキャリアの面での感想とメリットを書いてみたいと思います。
家族との関係が深まる
これはもう言うまでもありませんが、出産後すぐに育児にフルコミットする期間があることで、パートナーとの関係性や子どもとの絆がまったく違う形になります。夜泣き対応やオムツ替え、ミルク作りなど、最初は手探りで大変ですが、そこで得る“家族のチームワーク”は何ものにも代えがたい体験でした。
復職後もスムーズに働ける
長期にわたって育休を取ると「復職後の仕事はどうなるの?」と不安になります。しかし、実際に復職してみると、会社の仲間がその間の業務をカバーしてくれたことを感謝する気持ちが湧くと同時に、自分がいない間に進んでいたプロジェクトの新鮮な視点を得るチャンスでもありました。しばらく会社を離れたことで頭がリセットされ、よりクリエイティブに仕事に向き合えるようになったと感じています。
社内外からのサポートを受けやすくなる
前例の少ない男性長期育休は、最初はハードルを感じますが、実際に動き出すと「応援しています!」と声をかけてくれる人が少なくありません。自分が思う以上に、周りの人は協力的で、“新しいことに挑戦する人を後押ししたい”と考えてくれるケースが多かったです。これによって社内ネットワークが広がったり、今まで話したことのなかった他部署の人とも連携できたりと、“育休を機に世界が広がる”面白さを感じました。
おわりに
男性が長期の育休を取得することは、まだまだ珍しいケースだと思っている方が多いかもしれません。
しかし、実は制度は既に整いつつあり、あとは「どうやって実際に取得に踏み切るか」というフローを踏めばよいかが大きな課題です。本記事で紹介したタイムラインや、私自身が実際に経験した相談の仕方が、皆さんの参考になればうれしく思います。
繰り返しになりますが、いちばんのコツは“早めの相談”です。
パートナーの妊娠がわかったら、まずは心配事や不安を包み隠さず、信頼できる上司や人事に打ち明けてみましょう。「まだ周りに言えていないのですが」と特別感を出して話すだけでも、相手の態度は大きく変わります。そこから少しずつ、他の同僚やプロジェクトメンバーに情報を広げ、引き継ぎの準備を始める。そのプロセスに時間とエネルギーをかけることで、いざ育休に入ったときも、周囲の人が気持ちよくサポートしてくれる環境が整いやすくなります。
そして、ぜひ育休の期間は思い切り家族との時間を大切にしてみてください。仕事では得られない学びや発見が、育児には詰まっています。赤ちゃんの成長やパートナーの変化を間近で支え、一緒に喜び合う経験は、きっと今後の人生の大きな糧になるはずです。長期の育休を取りたいと思っている方は、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。必ずや得るものは大きく、復職後のキャリアにとってもプラスになることでしょう。
男性が育休を取ることはもう“珍しい挑戦”ではなく、当たり前の選択肢になりつつあります。
自分が実際に行動を起こせば、周りにも「こういうことができるんだ」という新しい気づきを与えられるかもしれません。一人ひとりのチャレンジが職場や社会を変えていくきっかけになり得るのです。
ぜひこの記事を参考に、ご自身のスケジュールと職場の事情に合わせた“オリジナルの育休取得プラン”を立ててみてください。長期の育休は、その分だけ家族とのかけがえのない時間をつくり、同時にあなた自身の人生やキャリアにも新しい可能性をもたらしてくれるはずです。応援しています!