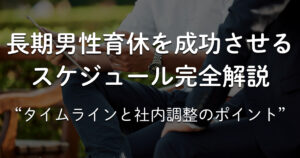男性が長期の育休取得を検討する時、やはり気になるのが収入面。
いろんな制度がありそうだけど・・・自分の場合結局いくらもらえるの?
どうすれば手取りを増やせるの?
そんな不安を解消するための「男性が育休中の手取りを増やす方法」シリーズの第1弾として、育休取得時に活用できる「育児休業給付金」について詳しく解説します。
実際の厚生労働省のガイドラインや最新の情報を参照し、どのように支給額が決まるのか・社会保険料の免除などによって実質的な手取りはどれほどになるのか、というポイントをわかりやすくまとめました。
特に「高年収の方ほど給付金の上限に引っかかりやすい」「半年以降は給付率が下がる」といった注意点もあるため、自分や家族の状況に当てはめて考えてみてください。
(※この記事は執筆時点の情報をもとにしています。法改正や運用の変更等がある場合は、最新の厚生労働省や自治体の公式情報を必ずご確認ください。)
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、赤ちゃんの誕生後に会社を休んで子育てに専念する際、“国”から支給される給付金です。意外に見落とされがちなのが「会社からの給付ではない」という点。
会社員として働いている人(雇用保険に加入している人)は、育休中に会社から給料が出ない代わりに、国の制度として給付金がもらえる仕組みになっています。
男性が育休を取るか迷うとき、まず一番気になるのは「お金」の話ですよね。「収入がなくなったらどう生活していけばいいの?」と不安になるのは当然です。ところが、この育児休業給付金を利用すれば、たとえ半年〜1年程度の長期休暇を取得したとしても、収入が“ゼロ”にはならないように配慮されています。
ただし、勘違いしている人も多いのですが、育児休業給付金はあくまで休業前の給与を何割か保証する仕組みであって、給与と同額がもらえるわけではありません。さらに上限額が設けられているなどの注意点もあるので、まずは基本的な計算式や仕組みを押さえておきましょう。
育児休業給付金の支給額の計算式
育休中の給付金は、大きくわけて「育休開始から180日目まで」と「181日目以降」で計算式が変わります。厚生労働省が公表している計算式は以下のとおりです。
- 育休開始から180日目まで
支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% - 育休開始から181日目以降
支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」という言葉は少し分かりにくいですが、要するに「育休を開始する前の半年間で、1日あたりいくらくらいの賃金を受け取っていたか」という平均値です。具体的な算出方法は以下のイメージになります。
- 育休開始前の直近6ヶ月間に支払われた“額面の賃金”の合計を180で割る
- 額面(総支給額)には、基本給に加えて、残業手当や通勤手当、住宅手当なども含む
- 控除後の“手取り”ではなく、社会保険料や税金が差し引かれる前の金額を使う
この計算で1日あたりの賃金を出し、さらにその月の日数を掛け合わせ、その上で67%(半年を過ぎると50%)をかけた額が、その月の給付金として振り込まれるイメージです(支給日数は厳密には1カ月ごとにカウントする支給単位期間ですが、大きくずれないため「月の日数」と考えておくとわかりやすいでしょう)。
上限額に要注意:高年収ほど損をしやすい
実はこの育児休業給付金には、支給日額の上限が定められています。
2023年(令和5年)時点では、1日あたり15,690円が上限とされており、ひと月あたりの上限はおよそ30万〜31万円程度です(1カ月を30日で計算した場合、15,690円×30日=約47万円ですが、そこから67%が適用されるため約31万円が目安)。
このため、たとえば平均給与が100万円の人であっても、計算上は「67万円」とはならず、最大でも30万円ちょっとが支給額の上限になってしまいます。つまり、給与水準が高い人ほど「67%」という数字どおりにはもらえないケースが多いのです。
加えて、181日目以降の給付率が50%に下がる時期になると、上限に達しやすいかどうかは関係なく、単純に「67% → 50%」まで大きく減額されます。ここでも日額上限の15,690円は変わらないため、上限にかかる場合はさらに最大の月額が少なくなり、月額ベースで約23万円ほどが限度になることも頭に入れておきましょう。
ワンポイントメモ
- 上限額は法改正や毎年の見直しなどで数百円〜千円単位で変動する可能性があります。厚生労働省の最新資料や公式サイトで随時ご確認ください。
育児休業給付金の“いいニュース”:社会保険料が免除される
支給率が67%や50%に下がる点に不安を覚える方もいるかもしれませんが、実は育児休業給付金は給与ではないので税金や社会保険料が大幅に抑えられるというメリットがあります。具体的には以下の項目が大きく変わります。
- 雇用保険料・所得税がかからない
給付金は課税所得ではないため、所得税も雇用保険料もゼロ。つまり、受け取った額面がそのまま自分の手元に残るイメージです。 - 健康保険料と厚生年金保険料の免除
これらは会社員が毎月必ず支払っている大きな出費ですが、育休取得中は「申請」により全額免除されます。つまり、普段であれば給料から天引きされていた分が差し引かれないので、その分だけ手取りが増えた感覚になるはずです。- 免除期間は産休・育休を開始した翌日が属する月から、復帰した前日が属する月の前月まで、など細かな取り扱いがあるため、会社の総務や人事部、または加入している健康保険組合に必ず確認しましょう。
- 免除期間は産休・育休を開始した翌日が属する月から、復帰した前日が属する月の前月まで、など細かな取り扱いがあるため、会社の総務や人事部、または加入している健康保険組合に必ず確認しましょう。
- 住民税は前年収入ベースなので要注意
唯一、住民税だけは前年の収入をもとに計算されるため、育休中でも支払う必要があります。月々の給与明細から住民税が天引きされない場合は、前後に自治体の納付書が届くこともあるので、忘れずに支払いましょう。ただし次年度以降は育休期間中の「非課税期間」がある分、住民税が安くなる場合があります(事前の給与額や給付金以外の収入にも左右されるので、シミュレーションが必要です)。
こうした各種保険料の免除も合わせて考えると、実質的な手取りが「育休前の8割ほど確保できた」という人も少なくありません。もちろん、高額な給与をもらっている方は上限にかかりやすかったり、半年を超える取得分は給付率が下がったりと不利な点もあるため、個々の状況に合わせた試算が大切です。
実際にどのくらい手元に残る?試算の例
例1)月額の額面が30万円程度の方が半年育休を取るケース
- 育休開始前の6ヶ月間の総支給額(額面)が約30万円×6ヶ月=180万円
- 日割りすると、180万円÷180日=1万円/日
- 月の支給日数を30日と仮定すると、1万円×30日=30万円
- これに67%を掛けると、約20万1千円が1〜180日目までの月あたり給付額となる
- 社会保険料や所得税が免除されるため、手取りベースでは一般的に育休前の8割ほどに近づく(ただし住民税の支払いは必要)
例2)月額の額面が50万円以上の方が半年〜1年育休を取るケース
- 日額上限(15,690円)を超える方は、67%という計算があってもそこには上限があるので、月にすると最大で約31万円程度
- 181日目以降は50%に下がるため、月あたりの受給額はさらに下がり約23万円程度が上限になる
- 高収入の方ほど「67%」や「50%」という数字通りには受け取れず、実質的な保証率は低くなる
- ただし、やはり社会保険料が免除されるので、現金支出の面では多少の救済はある
育児休業給付金を受け取る際の手続きの流れ
育児休業給付金を受け取るためには、会社経由でハローワークに申請書類を提出してもらう必要があります。おおまかな流れは以下のとおりです。
- 会社に「育休取得」の意思を伝える
- 取得期間や復帰予定日をある程度決めておき、就業規則に沿って申請する
- 取得期間や復帰予定日をある程度決めておき、就業規則に沿って申請する
- 会社から雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書などの書類を作成してもらう
- 必要な書類や手続きは人事部や総務部が詳しいので、わからないことは早めに確認
- 必要な書類や手続きは人事部や総務部が詳しいので、わからないことは早めに確認
- ハローワークに申請書を提出する(会社が代行する場合が多い)
- 育休が始まったあと、2ヶ月ごと(支給対象期間ごと)に申請書を提出することで給付金が振り込まれる
- 申請が遅れると振込が遅れることがあるので要注意
細かな手続きは会社の担当部署が補助してくれるケースが多いですが、提出に必要な書類や期限は自分でもしっかり把握しておくと安心です。
まとめ:給付額だけでなく“非課税&免除”も含めたトータルで考えよう
育児休業給付金は、長期間育児に専念するための大切な“経済的後押し”となる制度です。額面上は「67%」や「50%」と聞くと心配になるかもしれませんが、所得税や社会保険料が免除されることを踏まえると、実質的に受け取る手取り額は思ったより悪くない、という声が多くあります。とくに収入がそこまで高くない場合は、給付金と保険料免除が合わさって、育休前の8割程度の手取りを確保できたという人も少なくありません。
ただし、高年収の場合や半年以上の長期育休を検討する場合は、上限額の影響や給付率ダウンによって、実質的にはさらに低い保障になる点は要注意。また、育児休業給付金の上限や計算方式は時期や法改正によって変わる可能性もあるので、最新の情報は厚生労働省のパンフレットや公式サイト、あるいは会社の人事部などから定期的に確認しておくことをおすすめします。
- 厚生労働省:社会保険料や税金についてのパンフレット(令和5年版の例)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
「育休中はお金が入ってこないから厳しい」とあきらめる前に、ぜひ国や自治体の制度をうまく活用してみてください。家族にとって大事な時期を経済的に不安なく過ごせるよう、まずは育児休業給付金の仕組みをしっかり理解して、一歩踏み出してもらえればと思います。
これから長期の育休取得を検討する方は、今回ご紹介した計算式と注意点、そして“良いニュース”である保険料免除などをセットで押さえておきましょう。特に男性育休を取る方にとっては「思ったより生活できる!」という声も増えてきています。家計の計算をしっかり行い、制度や税金の仕組みを上手に利用して、“手取りを増やす工夫”をすることこそが、育休生活をより充実したものにする鍵となるはずです。
本記事では、育休中の収入がどう変わるのか、そしてどれくらい実質的な手取りが確保できるのかについて解説しました。しかし、実際に育休取得を決める際には、「家庭の貯蓄やパートナーの収入」「いつまで育休を取るのか(期間)」「復職後のキャリアプラン」など総合的に考える必要があります。次回以降の記事では、手取りを増やすための実践的なコツについても掘り下げていく予定です。